オニパンカフェ開店当時のイチオシアイテムの一つにカレーパンがあった。私自身がカレー好きで、以前より、パン屋に出くわせば、必ずといっていいほどカレーパンを食べた。自分でつくれる数少ない手料理のメニューの中で、カレーだけは自信があった。子どもの頃から、好きな食べ物として、一にカレー、二にラーメン・・・・、と、私の人生の中でも、カレーは特別な位置にある。だから、パン屋になったら(なれたら)、カレーパンはおいしくつくるぞという強い思い入れがあった。
そして、パン屋開店。オニパンカフェの案内リーフ(当時)にカレーパンのことを載せた。

2週に一度くらいの割合で、この2年間カレーを作ってきた。
半年くらいで、カレー作りに限界を感じ、イチオシアイテムから撤退。
色々試してみたが、美味しくならない。もちろん、まずくはないが、うま~い!とは感じられない。自分がおいしいと感じられない商品をカウンターに並べるのは辛いものがある。
リーフは、開店より半年くらいして、書きかえられた。

最近、APU(アジア太平洋大学)のタイウィークに行った。タイ料理がお目当てだ。そこでタイカレーを食べた。初め甘くて後からピリッとする辛みが口に残る。辛いが後味はとてもいい。タイカレーってうまいなあと思った。さらに2週ほど後、たまたま湯布院の「原っぱカフェ」の企画でカレーを食べる催しがあった。そのカレーもタイカレーだった。辛いが、これまたうまい!なんだこのうまさは!
食べ始めの甘い味は、ココナッツミルク。そして、辛さは、数多くの香辛料から。隠し味は、ナンプラーのようだ。家でもタイカレーを作って食べた。今までのカレーとは一線を画すうまさ!この味をカレーパンに取り入れられないものか。
私は、開店当初のように、希望に燃えて、カレー作りにいそしんだ。この2年間で、まとまったオニパンのカレーレシピを基本にしながら、ココナッツミルクやタイカレーのペースト、そしてナンプラーを加え、オニパンの甘いカレーから、ちょと辛めのカレーへと転換させる。自分で食べても結構満足のいく出来栄えとなった。
わくわくしながら、翌日は、初めてのタイカレー(風)パンをカウンターに並べた。
それから数日、リピーターの佐賀県から来るKさんが、またやってきた。Kさんはタイカレーパンが初めて並んだ日に、塚原に用があってオニパンカフェに立ち寄ってくれた。そして、たくさんのパンを買っていただいた。そして、また立ち寄ってくれたわけだ。Kさんは「パンおいしかったですよ。特にカレーパンはとてもおいしかった。お肉がごろごろ入っているカレーパンより、後味もよく、また食べたくなるおいしさでした。」もっとたくさんお話していたが、とにかくうまいという評価をいただけた。いっぱい買って帰ったパンの中で、わざわざカレーパンのことを評価してお話してくれたのには、驚いた。
タイカレーパンは、まだまだ試作段階。レシピが定まったわけではない。しかしこんな風にカレー作りができるようになって、人生簡単にあきらめてはだめだなあと考えさせられた出来事でもあった。

フィリング作りの中で、最も大変なのがカレー。大変な労力を注ぎ込んでいる。そのカレーに自信が持てないという日々が続いていた。でもこれからは違うぞ。この暑さも乗り切れる、甘くて辛い、そしてうまい、オニパンカレ―パンの登場だ!さあ、どうだ!ウ~と唸るおいしさだぞ。君も食べてみないか、オニパンのタイ風カレーパン。きっと、君のハートに台風のごとき感動が訪れるぞ!(以上、宣伝でした)



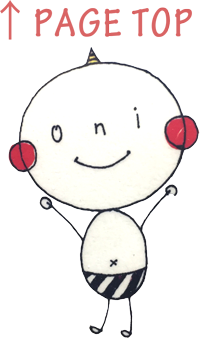
営業時間 10:30〜16:00
定休日 火・水・木(※木は予約販売受取のみ)
(※祝祭日は営業します)