一年に一回か二回の折々帳。ついにそうなってしまった。200回を目指してやってきたのだが、たぶんあと30年はかかる。ほぼ100歳か。私の命はあと何年なんだろう。たまたまサイクリストのために始めた道路状況のInfoは、気がつけば6年。日に日に内容が深まり、数も1472号。折々から、日々の記事に。まあこういう形でもオニパンの足跡を残していけるわけで。
しかしこの記録を残して何か意味があるのだろうか。そうも考える。誰が読み返すのだろう。それはないな。折々帳といい、Infoといい、すべては自分のため。そのときどきの振り返りの場、振り返りの時間、そしてこれから進みゆく自分の方向を定める推考のひととき。
新年の折々帳は、この来るべき一年の目標・計画・ロマンを語る場となってきた。そして、昨年、一昨年の折々帳を読み返すと・・・・
実に驚く。まさにそのとおりになっている。ホラでも何でもなく、着実に現実のものに。実現可能な計画を立て、それに一歩足を踏み出す。それは、もうすでにユメではなく現実。100%パーフェクトはないだろうが、10%、20%~70%とユメは現実に。だから、大事なことは足を踏み出すこと。そういう確信が生まれてくる。

この小麦畑にしてもまさか自分で小麦を作れるのかとの思いがあったが、やりはじめると、できる!6回の経験はよりよきおいしい小麦を作り出している。「ユメ食パン」の注文が最近入り出した。確かにおいしいもの。
人生ってそう考えると、躊躇は必要ないな。少しでも自分のやりたいと思うことを、現実的な計画を立て、実践する。さすれば出来る。最近読んだ文章の中でとても感銘する言葉があった。「諦めなければ、それは勝てる(実現する)」。諦めるということをしなければいいのだ。そういえば、私が折々に参考にしてきた「ベーカリーパートナーの部屋」というネットサイトのパンの達人の言葉も通じるものがある。彼はベーカリーの成功の秘訣は?との問いに「パンの技術や経営面の研究とかではないなあ」「結局うまくいかなくなる困難な場面は必ずでてくるわけで」「私が思う一番の秘訣は根性かな」「何があってもくじけないという気持ちの強さがパン屋成功の秘訣」そんな感じで書いていた。なにかいい方法や成功への筋道みたいなものがあるわけでなく、くじけない心、目標達成への強い思いなのだと。
Infoでも書いたことがあった「小さな会社の生きる道」という本のこと。その本を読んで現在のオニパンの状況を整理している。お店を車に例えるとお店をうまく進めていくためには商品開発や目指す商品の方向性が必要だ。おいしい、お客様の求める商品の創造。お店のコンセプト。そしてどんな売り方をしていくかという商売のやり方。お店の作り方、移動販売などもそれに入るだろう。いわばそれは、車の前輪。しかし、それだけでお店がうまくいくわけでない。オニパンが目指す商品のブランド化や魅力の商品開発、オール国産小麦などにチカラを注ぐだけではお店は安定しないだろうな。
お店でむずかしいのは、むしろ後輪の部分。経営の効率化、製造手段や製造方法の改善、働き方の改善(労働意欲に直結するものなあ)売り上げ増のための方策・・・もう、私も頭が痛くなる。これもそれなりに取り組んできた。例えば、冷蔵生地や冷凍ストック、仕込み回数減。しかし、なかなか改善の域までいかない。誰かにアドバイスをいただきたいものだ。

これで、料理や荷物の運びが楽に。

具体的な目標計画はおいといて、とにかくこの車の前輪と後輪をしっかりさせていくのが、今年のオニパンの課題。というのも、3人目の従業員さんが加わり、それなりの運営をしていかねばならないからだ。私たち老ママと老マスターの健康維持のための労働軽減も視野に入れ。
さらに、付け加えていうならば、車の前輪、後輪部分をしっかりさせるだけでは、意味がないなということ。お店が安定して維持でき、そこで働く人たちの暮らしを守り、お客様に喜んでいただくことは前提部分。この正月休みにママといろいろ話した。お店が維持できることが基本なのだが(潰れてしまってはなにもできない)、その後このオニパン号はどこへ向かって車を走らせていくのか、それこそが私たちの人生の目的ではないのだろうか・・・そんなことを話した。
このことも、近いうちに実践していこう。ぼちぼちと。やれば出来る。やり出したら出来る。10%でも。ちょっと謎めいた書き方になっているが、まだ、いえるほどの煮詰め段階にいたってないから。でもやるぞ。


なくなってしまいました。怖かった~。木こりのダイさんみたい
なことをしてしまった。

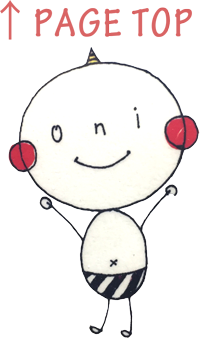
営業時間 10:30〜16:00
定休日 火・水・木(※木は予約販売受取のみ)
(※祝祭日は営業します)